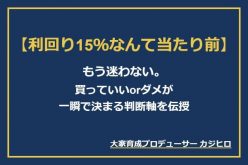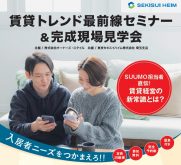住宅・土地統計調査で空き家数900万戸と過去最多に。空家特措法改正から半年、空き家対策はどう進む?

総務省が5年に1回実施している「住宅・土地統計調査」の令和5(2023)年版の速報集計が発表されました。それによると空き家数は900万戸と過去最多を記録。前回2018年の調査から51万戸も増加していることが明らかになりました。2023年12月に空家特措改正法が施行されましたが、はたして空き家対策は進んでいるのでしょうか。
「住宅・土地統計調査」とは

住宅・土地統計調査は、国の統計に関する基本的な法律「統計法」にもとづいた基幹統計調査です。基幹統計とは、総務大臣が指定する特に重要な統計のことで、住宅・土地統計調査は昭和23(1948)年から5年ごとに行われ、今回の調査は16回目の調査にあたります。
住宅・土地統計調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の目標設定や耐震や防災などの都市計画の策定、空き家対策条例の制定のための基本資料として利用されています。
前回調査は2018年。今回は令和に入ってから初めての調査で、コロナ禍を経た世帯や住宅に関する変化が反映されていると思われます。
この5年間で住宅が最も増えたのは沖縄県
現在は速報集計ということで、都道府県の総住宅数、空き家数などが確定値に先駆けて公表されました。確定値は9月ごろに公表予定です。
ざっとご紹介すると、日本の総住宅数は2023年10月1日現在で6,502万戸。2018年から4.2%(261万戸)増加しました。総住宅数はこれまでも一貫して増加が続いており、今回も過去最多を更新しています。
都道府県別にみると、東京都が820万戸と最も多く、それに大阪府493万戸、神奈川県477万戸が続きます。

増加率で見てみると、2018年からの5年間で最も高いのが沖縄県の7.2%。次いで東京都が6.9%、神奈川県及び滋賀県が5.9%となっています。増加率がマイナスとなったのは青森県、秋田県、高知県、長崎県の4県でした。
【登録はすべて無料】オーナーズ・スタイルでは様々なメディアで情報を発信中!
| お役立ち情報を 週2回無料で配信中! |
約100ページの情報誌を 年4回無料でお届け! |
||
| オーナーズ・スタイル お役立ちメルマガ
|
賃貸経営情報誌 オーナーズ・スタイル
|
空き家数・空き家率とも過去最高に!

注目すべきは空き家率。空き家の増加はすでに社会問題となっており、2023年12月に空家特措改正法が施行。特定空き家や管理不全空き家に対する市区町村長の対応権限が拡大されています。
また、2024年4月から施行の相続登記の義務化も、持ち主が亡くなった不動産が空き家や所有者不明土地になってしまうことを防ぐことが目的です。
総住宅数のうち空き家は900万戸と、2018年(849万戸)から51万戸増加し過去最多に。総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)も13.8%で、こちらも過去最高となりました。空き家の数は、1993年から2023年までの30年間で約2倍になっています。
空き家の定義には、賃貸や売却のために一時的に人が住んでいない住宅や、別荘・セカンドハウスなども含まれますが、それらを除いた「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は385万戸でした。こちらも2018年(349万戸)から37万戸増加し、総住宅数に占める割合は5.9%となっています。
空き家率は西日本で高い傾向に
空き家率を都道府県別にみると、和歌山県と徳島県が21.2%と最も高く、次いで山梨県20.5%が続きます。
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」は鹿児島県が13.6%と最も高く、次いで高知県が12.9%、徳島県と愛媛県が12.2%。空き家率は西日本で高い傾向となっています。
一方、空き家率が最も低いのは沖縄県で9.3%。次いで埼玉県9.4%、神奈川県9.8%が続き、1割未満だったのはこの3県のみでした。
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」では東京都が2.6%と最も低く、神奈川県3.2%、埼玉県3.9%が続いています。
相続登記義務化を知る空き家所有者では6割

「住宅・土地統計調査」により、空き家がさらに増加していることが分かりました。空き家については前述のとおり、2023年に空家特措法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律)が改正、2024年4月から相続登記が義務化されました。空き家所有者の意識に変化はあるのでしょうか。
これについては、空き家の買取り事業などを行う(株)カチタスが、全国の空き家所有者を対象に毎年行っている「第4回 空き家所有者に関する全国動向調査(2024年)」を見てみましょう。
空き家の取得経緯で最も多いのは「相続」で77.8%、相続登記義務化を知っていると答えた空き家所有者は58.9%でした。調査開始(2021年)から約2.5倍に増えており、認知が広がっているようです。
空き家の相続について家族と対話をしている人も71.8%となり、過去最高値となりました。3年で約2倍に増加しており、空き家の相続に対する意識は高まっているとみて間違いないでしょう。
空き家特措法が改正されたことを「知っている」と答えた人は52.1%で、こちらも前年の38.4%より認知度が上がっています。
空き家対策が進まない理由はどこにある?
同調査では、空き家の相続について家族と対話をしている人としていない人の比較も行っています。空き家について「売却」「賃貸」などの対策を決めている人の割合は家族と対話している人の方が多く、していない人の1.4倍にもなっています。つまり、空き家の対策を進めるためには「家族との対話」が必要であると考えられます。

「家族の対話」をしたことがない理由のうち、最も多いのは「まだ先のことだから(37.2%)」。年代別で比較すると「まだ先のことだから」を最も多く選択したのは60代以上(47.1%)でした。国土交通省が実施した「令和元年空き家所有者実態調査」によると、60代以上のシニア層は空き家所有者の約7割を占めています。
このことから(株)カチタスは、空き家を減らすには「シニア層による問題の先送り化」への対策が必要、と分析しています。
まとめ
「住宅・土地統計調査」では、空き家がさらに増えており、その増加率も上がっていることが分かりました。しかしその一方で、空き家特措の法改正や相続登記義務化などにより、所有している空き家をどうにかするための対策を講じ始めた人も増えつつあるようです。
空き家所有者に対する動向調査では、法令への認知と家族との対話が進むほど、空き家の利活用の検討者も増加していることも明らかになりました。まずは身近な空き家対策として、「知る」こと、「話す」ことが有効なようです。今は空き家を所有していなくても、将来、実家をどうするかなどについて、家族と日常的に話しておくと安心です。
※この記事内のデータ、数値などに関して本記事は、2024年5月15日時点の情報をもとに制作しています。
文/石垣 光子
ライタープロフィール
石垣 光子(いしがき・みつこ)
情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。
【登録はすべて無料】オーナーズ・スタイルでは様々なメディアで情報を発信中!
| お役立ち情報を 週2回無料で配信中! |
約100ページの情報誌を 年4回無料でお届け! |
||
| オーナーズ・スタイル お役立ちメルマガ
|
賃貸経営情報誌 オーナーズ・スタイル
|