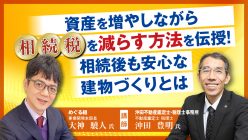税理士が伝授!知っておくとラクになる確定申告のコツ~領収書整理から修繕費の線引きまで、プロが解説~

確定申告は毎年の悩みの種。でも、ちょっとした工夫で驚くほどラクになります。領収書整理から修繕費の扱い、2025年改正ポイントまで、税理士が実例を交えてわかりやすく解説。賃貸オーナー必見の「申告ストレス軽減術」です。

税理士法人アンサーズ会計事務所 代表税理士
野上 浩二郎 氏
慶應義塾大学卒業後、大手税理士法人にて相続・事業承継・不動産に関わる税務等を中心とした業務に従事。相続・事業承継の豊富な実績を経て、2012年に税理士法人アンサーズ会計事務所を設立。資産家や中小企業オーナーの相続・承継の課題解決に尽力している。著書に「専門家のための事業承継の実務」(翔泳社)、「事業承継の失敗事例33」共著(東峰書房)等。
確定申告に向けておさえておきたいポイント
皆さんこんにちは。税理士の野上です。今回は、確定申告に向けて日ごろから気を付けておくとグッと楽になるコツと、2025年分で大家さんが知っておきたい改正ポイントをまとめてお伝えします。
①領収書の整理は「こまめ&二重計上防止」
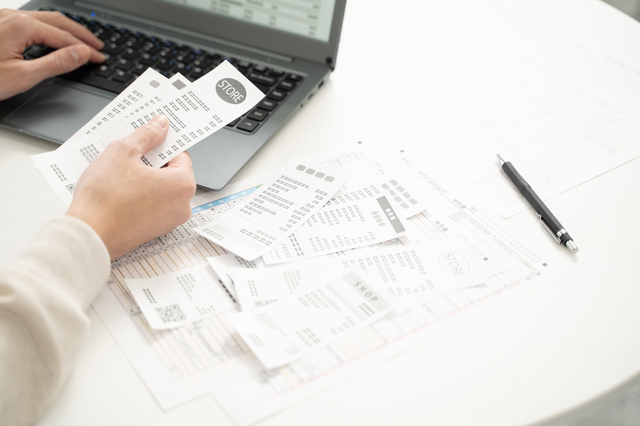
賃貸不動産に関係する支出は、不動産所得の経費になります。まずは証拠となる領収書や請求書等をきちんと保管する習慣をつけましょう。
領収書等を一緒くたにして袋にまとめて入れておくだけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合、後からつまずきがちなので、勘定科目ごと(交際費・消耗品費・旅費交通費など)に仕分けをし、日付順で整理しておくのがおすすめです。
クレジットカードの利用明細やネットバンキングの入出金明細を「証拠」にしている方は、領収書との二重計上をしないように注意してください。月次で一度、科目ごとの合計を出してみて「漏れ」と「ダブり」をチェックする習慣
をつくっておくと、年末に慌ただしくならずにすみます。
ポイントはため込まないこと。一年分の山を一気にやると、「これ何の費用だっけ?」となりやすいので、毎月月初に前月分の整理をするなど、「ミニ締め」習慣を作ると楽になります。
②インボイスの有無を「整理の段階」で仕分け

課税事業者の方は、インボイスの有無確認の作業を避けて通れません。領収書整理のときに、「インボイスあり/なし」を箱やファイルで分ける、または一覧にチェック欄を作っておくと、仕訳時に迷いません。駐車場の貸し付けや事務所賃貸など消費税の課税売上が混じる方は、その辺りを意識して整理してみてください。
なお、免税事業者からインボイス登録した小規模事業者向けの「2割特例」は2023年10月1日~2026年9月30日開始の各課税期間が対象となっています。特例の適用期間もあと一年間。2割特例の適用期間終了後の税負担の増加見込みを踏まえ、「簡易課税制度」の選択の検討や課税事業者選択の見直しを早めに試算しておくと安心です。
③「資産計上するもの」の区分けを行う
備品購入時の原則的な処理は次のとおりです。
消耗品費として全額経費計上。
固定資産に計上し、減価償却により費用化。
一括償却資産として3年間で均等費用化が可能。
少額減価償却資産の特例を利用して30万円未満まで即時償却が可能(年300万円まで)。
エアコンや給湯器、複数年使う家具・家電などは資産計上の候補です。
30万円以上のものは固定資産計上が必須なので、「支出の金額=経費計上額」にはならないということを頭に入れておきましょう。
④修繕費と資本的支出の線引き
賃借人の入退去のタイミングや、数年に一度の大規模修繕など、不動産賃貸業には修繕がつきものです。税務上は、同じ「直した」でも、修繕費(全額その年の経費)になるのか、資本的支出(資産計上して減価償却)になるのかで、その年の所得計算の結果が変わります。
原状回復や性能維持のための補修は修繕費になりやすく、耐久性アップや価値向上につながる工事等は資本的支出になりやすい、というのが基本的な考え方です。
特に大きな工事をする時には見積もりの段階で「修繕か資本的支出か」を意識し、最終的に今年いくら経費に計上できるのかを計算しておきましょう。そうすれば、申告時に「思っていた以上に税金がかかってしまった」と焦ることを避けられて、安心です。
2025年分の気になる改正ポイント

基礎控除の引き上げ
所得税計算上の基礎控除が10万円引き上げられました(改正前48万円→改正後58万円)。※2025~26年は、所得に応じて段階的な基礎控除の上乗せも行われます。
また、給与所得控除の最低保障額も、10万円引き上げられました(改正前55万円→改正後65万円)。
扶養範囲の基準変更
前述の改正の影響で、「扶養」に入れる人の基準も変わりました。これまではいわゆる「103万円の壁」(給与所得控除の最低額55万円+基礎控除48 万円=103万円)により、配偶者や子どもが給与収入のみの場合には、その給与収入が103万円以下、というのが扶養に入れるボーダーとされていました。これが改正により「123万円の壁」(給与所得控除65万+基礎控除58万=123万円)へ引き上げられました。
「特定親族特別控除」の新設
「特定親族特別控除」の新設により、19歳以上23歳未満の子どもについてはボーダーがさらに引き上げられ、段階的に控除額が縮小されるものの、給与収入が188万円以下であれば控除が適用できるようになりました。アルバイト収
入があるお子さんがいらっしゃるご家庭は、家族の収入見込みを早めに確認しておきましょう。
最後に
なにごとも、対策は時間的な余裕があればあるほど有効な手立てを講じやすいです。何か節税対策をしたいと思っても、年末を過ぎてしまっては取れる対策はかなり限られてしまいます。こまめに処理を進め、定期的に損益状況を把握しておきましょう。
毎年、確定申告時期が憂鬱という方も多いと思いますが、早めに処理を進めておくと、精神的にも余裕を持って確定申告時期を迎えられるのでオススメです。
※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年11月1日時点のものです。
イラスト/さかちさと