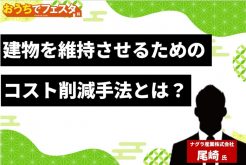騒音・ゴミ出し・臭い…。生活習慣や文化の違いから生じる、外国人入居者とのトラブルの実態と解決策

住民基本台帳によれば、令和7年1月1日時点の日本国内に居住する外国人住民の人口は、233万2,294世帯と、身近な存在になりつつあります。その一方で、生活習慣や文化の違いによる摩擦やトラブルも増加していることも事実です。今回は外国人入居者との間に生じるトラブルの詳細と対処方法について、(株)Alba Linkが実施した「外国人入居者とのトラブルに関する意識調査」をもとに探っていきます。
約3割の人が外国人入居者とのトラブルを経験
賃貸住宅に暮らす500人を対象に、外国人入居者との間にトラブルを経験したかと聞いたところ、約3割の人が「ある」と回答しました。
| Q.外国人入居者とのトラブルを経験したことがあるか | |
| ある | 31.6% |
| 経験はないが周囲で聞いたことがある | 31.2% |
| ない | 37.2% |
さらに「経験はないが周囲で聞いたことがある」と答えた人が31.2%いたことを考えると、実際の経験者がそれ以上の数にのぼることは容易に想像できます。
1番トラブルになりやすいのは騒音で7割以上
3割以上の人が経験している外国人入居者とのトラブルですが、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。圧倒的な1位となったのは、71.4%の人が経験したという「騒音」トラブルです。
| 外国人入居者とトラブルになりやすいこと |
||
| 1位 | 騒音を出す | 71.4% |
| 2位 | ゴミ出しルールを守らない | 33.0% |
| 3位 | 共用部分の使い方が悪い | 9.0% |
| 4位 | 臭いがきつい | 7.8% |
| 5位 | 物件のルールに違反する | 4.0% |
n=500(複数回答)上位5位
「足音や生活音が大きく、階下に響く(30代・女性)」「スマホでの会話でも、スピーカーにして大きい声でしゃべる(40代・男性)」といった日本人同士でもありがちなものから、「隣人がブラジル人で毎晩ノリノリの音楽を大音量で流していることがきっかけで揉めた、と聞いた(20代・男性)」などの、国民性に左右されがちなものまで、詳細は多岐にわたります。
音に対する感覚や閑静な住環境の重要度は、文化によって大きく異なります。さらに日本に多い木造住宅では音楽の音はもちろん、足音や排水音なども容易に響いてしまいます。

しかし、外国人入居者が「日本の家は音が伝わりやすい」などの構造面の特徴を理解していない場合、外国人にとっては普通の生活音を出しているだけでも、近隣には“騒音”と感じられてしまいます。
外国人にとっては、普通に生活しているという認識のため、連日連夜続くことも普通で、迷惑と感じている側のストレスはたまり続けることに。そしてある日、トラブルという形で表面化してしまうのです。
「ゴミ出し」の細かいルールもトラブルの原因に

トラブルとして次に多く挙げられたのが「ゴミ出しルールを守らない(33.0%)」でした。
「曜日を守らず、カラスに荒らされる(30代・女性)」「夜中とかにゴミ出ししていて、ダンボールはまとめていない(30代・女性)」「指定の袋を使用せず、回収されないから夏などは臭って不快(50代以上・女性)」など、細かいルールがあることからトラブルになりやすいようです。
さらには、翻訳アプリで注意を促しても、「ソーリー」と言われるだけで一向に改善されないなどのケースもあり、ルールを守っている側に大きなストレスになっています。
しかし、日本人ですら自治体をまたいで引っ越しすると、最初は知らず知らずのうちにルール違反をしがちなもの。それだけに母国のゴミ出しルールと大きく異なる場合では、混乱してしまうのも無理はありません。必要性を含めて理解してもらうには、なかなかに根が深い問題のようです。
共用部分の使い方、お香や料理の臭いもトラブルに結び付く
「騒音」「ゴミ出し」の次にあげられたのは、「共用部分の使い方が悪い(9.0%)」です。「自転車の駐輪場所や停め方(20代・女性)」「廊下やエントランスに私物を置く(50代以上・男性)」などは、日本人にとって「秩序を乱す行為」「美観を損なう行為」に見られることも少なくありません。
さらに「臭い」のトラブルを経験された人も。「お香やスパイスの臭いが洗濯物にうつる(30代・女性)」というように、宗教的な理由や食文化の違いは、その国の外国人にとっては生活の一部でも、日本人にとってはなじみの薄いもの。臭いに敏感な人には、ストレスになってしまいます。
「多言語によるルール説明」が最善の対策方法
外国人入居者との間に生じたトラブルについて見てきましたが、その対処方法としてはどのようなものが挙げられるのでしょうか。
| 外国人入居者とのトラブルを防ぐために有効なこと | ||
| 1位 | しっかりルールを説明する | 55.4% |
| 2位 | 多言語で対応する | 28.0% |
| 3位 | 罰則規定を設ける | 14.6% |
| 4位 | 管理会社の適切な対応 | 9.0% |
| 5位 | コミュニケーションをとる | 7.8% |
| 6位 | 入居審査を厳しくする | 7.2% |
| 7位 | 居住エリアを調整する | 4.4% |
n=500(複数回答)上位7位
最も多く挙がった声は、55.4%と約半数の人が回答した「しっかりルールを説明する」でした。「複数回にわたる丁寧なルールの説明(40代・男性)」「ただ知らないだけということがよくあるので、最初にしっかり説明をする(40代・女性)」といったように、外国人に限らず日本人でも、こうしたことはあると考える人は多いようです。
具体的な解決例として、「外国人社員寮として使われている物件でゴミ出しトラブルがあったが、外国人の勤務先を通じて説明したら解決した」ということもあったそう。異なる文化圏から来た人の事情にも配慮しながら、相手に理解してもらう継続的な努力が大切だという考え方に基づいた意見です。
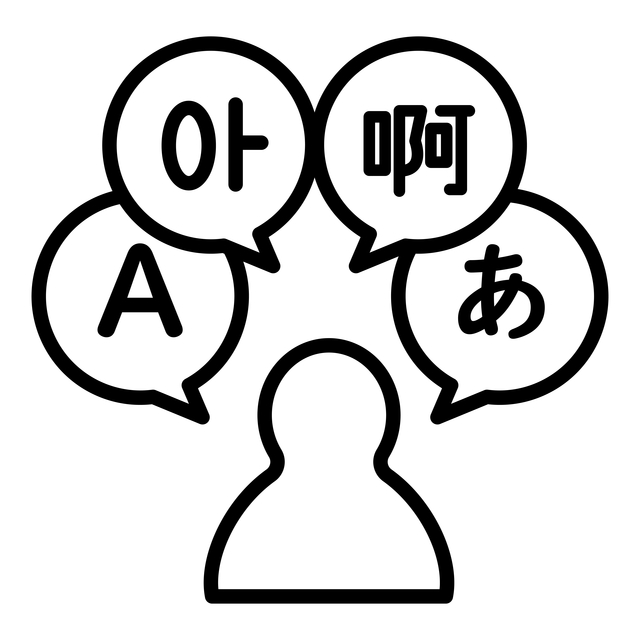
2位は「多言語で対応する(28.0%)」。「多言語でのゴミ分別マニュアルやゴミ分別カレンダーの完備。不動産会社に外国人専用相談窓口を設置(40代・女性)」「会社で借りている寮の場合などは、日本人の担当者を必ずつけて指導してもらう(30代・女性)」など、外国人に正確に理解してもらうには、母国語等によるコミュニケーションが必要不可欠と考える人は多くいます。
一部の不動産管理会社で導入済みの「翻訳アプリを使った24時間の外国人対応窓口」を評価している人もいました。
罰則規定や入居審査の厳格化などの意見も多数
“日本人同士でもよくある”“話せばわかってもらえる”といった意見が多数を占める結果となりましたが、それ以外に「罰則規定設ける(14.6%)」「入居審査を厳しくする(7.2%)」といった声も少なくありません。
「ルールを守れない人は強制的に退去。入国の際にしっかり理解してもらえるよう国で対策してほしい(50代以上・女性)」「厳しくしないと守らない(40代・女性)」「『自分ひとりでも日本語で日常会話が問題なくできること』を入居の条件に加える(20代・女性)」といった、罰則や入居審査を今以上に強化してほしいという声なども聞かれました。
その他にも「管理会社の対応力」や「日頃のコミュニケーション」といった声の他、「外国人入居者と居住フロアをわける(20代・女性)」「外国人専門の賃貸物件が必要(30代・女性)」など、人種差別を助長しかねない危険な意見も少数ながら聞かれました。
まとめ
今回の調査では、全体の約3割が外国人入居者とのトラブルを経験し、周囲で聞いたことがある人も含めるとそれ以上の増加傾向にあると思われます。
最も多いトラブルとして、育った国の文化や住環境の違いから感じ方に差が生じやすい「騒音(71.4%)」、次いで、日本人でも地域によって異なるルールに混乱しがちな「ゴミ出しルールを守らない(33.0%)」が多数を占める結果となりました。さらに共用部分の使い方や臭いなど、生活習慣の違いによる問題も少なくありません。
こうしたトラブルへの対策としては「ルールの丁寧な説明(55.4%)」や「多言語対応(28.0%)」など、文化差に配慮したうえでの継続的なコミュニケーションが重要と考えられています。一方で、罰則強化や入居審査の厳格化を求める声も少ないながらも見られました。
外国人との文化の違いを理解し、適切なルール整備を行うことが、安定した賃貸経営の第一歩です。多様性を受け入れながら、賃貸経営のリスクを減らす仕組みづくりを始めましょう。
※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年11月12日時点のものです。
取材・文/御坂 真琴
ライタープロフィール
御坂 真琴(みさか・まこと)
情報誌制作会社に25年勤務。新築、土地活用、リフォームなど、住宅分野に関わるプリプレス工程の制作進行から誌面制作のディレクター・ライターを経てフリーランスに。ハウスメーカーから地場の工務店、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、販売促進ツールなどの制作を手がける。