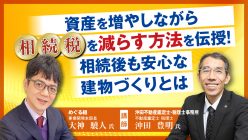家賃・管理費が過去最高額に。賃貸契約者が重視する“住まいの条件”とは?市場調査からトレンドを読む

SUUMOリサーチセンターが発表した「2024年度・賃貸契約者動向調査」によると、賃貸住宅の家賃および管理費(共益費)は、2005年度以降の過去最高額を更新。物価高や円安を背景とした住宅価格の高騰が今後も続くことが予想される中、賃貸住宅検討者は「住まい選び」においてどのように行動し、どのような条件を重視しながら契約に至っているのでしょうか。過去のデータと比較しつつ、最新のトレンドを読み解きます。
平均家賃は96,082円。管理費ともに過去最高を更新

(株)リクルートの住まいに関する調査研究機関であるSUUMOリサーチセンターが発表した、2024年度「賃貸契約者動向調査」によると、2024年4月1日から2025年3月31日までの間に賃貸契約を結んだ家賃の平均は96,082円で、前年度から3,500円以上上昇し、かつ2005年度以降で最高額となりました。
さらに、すべての世帯構成で前年度より上昇している中、とりわけファミリータイプの家賃が122,234円となり、前年の118,073円からは4,161円、2005年度からは23,467円と、その上昇の幅が大きくなりました。これは都心部を中心とした物件価格が、もはや一般世帯には手が出せないほど高騰したことにより、購入を断念して賃貸に切り替えた世帯が増加したことで、家賃が上昇したと考えられます。
また、管理費(共益費)も前年度から600円ほど上昇し、平均6,177円に。家賃と同じく2005年度以降の最高額となりました。加えて「管理費・共益費なし」という賃貸物件の数も、2005年度は30.4%ありましたが、2024年度では17.4%まで減少するトレンドに。金額面の増加だけでなく、「管理費・共益費なし」という物件自体も半数近く減っていることも明らかになりました。
「オンライン」を使用した訪問、内見、契約が前年より上昇
不動産会社への訪問数を見てみると、実店舗では1店舗の「53.6%」が最多に。平均1.3店舗は、前年度と同じという結果となりました。
その一方、オンラインでは店舗の未利用者が「62.1%」と最も多い結果となりましたが、1店舗以上利用した割合で見ると「37.9%」で、これは前年度から5ポイント以上の増加となっています。
さらに物件の内見においても、「オンラインと対面を併用」が9.1%だったのに対し、「オンラインのみ」は28.3%。合計は37.4%となり、前年度の29.0%と比較すると8ポイント以上も増加しており、2020年度以降で最多となりました。主流とは言えないまでも、4割近くの人はオンラインを利用していることが明らかとなりました。

「オンラインのみ」「オンラインと対面の併用」「対面のみ」の利用別で見ていくと、オンラインを含む2つの利用方法は、男性比率とペット飼育率が高い傾向にありました。
反対に「対面のみ」の利用者は女性(30代・40代)、2人世帯、アパート居住者が多いこともわかりました。ともに「じっくり探す派」という印象を受けますが、その中身には各属性による違いが出ているところが興味深いポイントです。
そして、契約におけるオンライン利用についても、「実際に利用したことがある(15.9%)」と「どのようなものか知っている(26.5%)」を合計した内容把握率が42.4%、「なんとなく聞いたことがある(34.4%)」を足した認知率でも76.8%と、2018年度以降で最多となっています。
内見まで進んだ物件数は減少傾向も、ここ数年は横ばい
次に、「住まい探しの際に見学した物件数(※0件を含む)」を見ていきましょう。2024年度は平均で2.6件となり、前年度と同じでしたが、2005年度以降はゆるやかな減少傾向にあります。世帯構成別で見ると「2人世帯」が2.8件で最多となっています。
ちなみに「物件を見学していない人」の割合は8.6%となり、こちらも前年度と同じでした。世帯構成別で比較すると、こちらも納得の「ひとり暮らしの学生」が18.7%で最多となりました。
「路線・駅、エリア」が契約の決め手。2年連続で増加
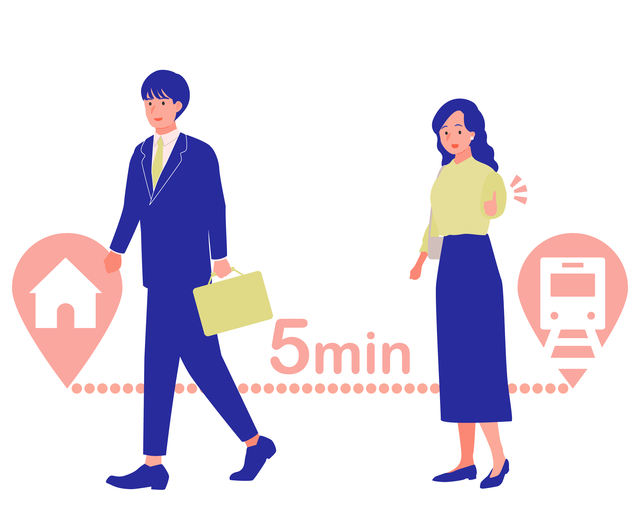
住まい選びの最終的な「決め手」となった項目の割合には、どのような変化があったのでしょうか。
1位は「路線・駅やエリア(54.7%)」で、2年続けての増加となっただけでなく、唯一の50%越えとなりました。次いで「最寄り駅からの時間(38.9%)」、「通勤・通学時間(30.4%)」、「初期費用(30.3%)」の3つが30%を超える回答率で続く結果に。
一方、「間取り(28.0%)」や「設備・仕様(8.2%)」が決め手となったと回答した割合は、ともに2021年度から約7ポイントの減少トレンドとなっています。これは前述した「利便性」を重視した結果の裏返しとも言えます。
世帯構成別に見てみると、男性社会人と学生(ひとり暮らし)は「通勤・通学時間」を、女性社会人と学生(ひとり暮らし)は「セキュリティ」をそれぞれ重視する傾向にありました。
対して2人世帯は「間取り」が契約の決め手となったとの回答が多く見られました。各属性に重視されるポイントを、それぞれの属性に好まれるエリアにあてはめていくという戦略が成り立つのであれば、これからの賃貸経営にも役立ちます。
満足度の高い設備に「24時間出せるゴミ置き場」など

設備に対する検討者の意向にも、興味深い結果が出ています。まず「実際に満足度の高かった設備」を見ると、「24時間出せるゴミ置き場」が最多の71.7%。これは「次引っ越す際に欲しい設備」でも上位にランクされており、注目に値します。「遮音性の高い窓(67.8%)」も同様の傾向を示しています。
一方で「エアコン(74.7%)」、「TVモニター付きインターフォン(61.2%)」、「フローリング(60.0%)」、「独立洗面台(59.3%)」、「2口コンロ以上(53.3%)」、「温水洗浄便座(51.2%)」は、すべて50%以上の設置状況となっており、もはや設置されていることが当たり前の設備となっています。
世帯構成別に見ていくと、ひとり暮らしでは「スマートロック」「オートロック」「ウォークインクローゼット」の満足度が高く、2人世帯では、「2口コンロ以上」「浴室乾燥機」「システムキッチン」などの他、「セキュリティシステム」「防犯カメラ」「ディンプルキーなどのピッキング対策の鍵」など防犯設備に対する満足度が高い傾向にあります。
ハザードマップの確認等、引き続き高まる防災意識
防災への意識や対策にも変化は見られたのでしょうか。
名称認知率(90.5%)内容把握率(74.5%)ともに高いハザードマップは、「自分で見た/調べた」と回答した人が48.3%と前年度から5ポイント上昇。昨今の線状降水帯や台風による深刻な被害が影響しているものと考えられます。属性別に見ていくと、男性よりも女性、さらには「ひとり暮らし」や「ファミリー世帯」で、全体よりも高い傾向にあります。
また、もはや異常ではなく通常とも言える“猛暑”などの気候変動に有効と考えられる「ZEH賃貸住宅」「長期優良住宅」「省エネ性能ラベル」は、世帯年収が高い層ほど、その内容把握率、名称認知率ともに高い傾向が示されました。
内見なしでは把握できない「事前に知りたかったこと」

最後に、「入居前に知りたいこと」について見ていきましょう。
最多となった項目は「日当たりや風通しなど、部屋の住み心地」で53.9%。次いで「最寄りの駅・バス停までの距離や経路(50.8%)」「近隣のスーパー・コンビニ・ドラッグストアなどの営業時間、距離や経路(50.6%)」で、この3つが50%越えという結果に。
属性別にみると、「女性」「対面での内見のみ」が全体に対して割合が高く、反対に「男性」「オンラインでの内見のみ」は低い傾向となりました。このあたりも適切な対応ができれば、契約時から入居後に至るまで、高い満足度が維持できそうです。
さらに「事前に分からず不便や不満を感じたこと」を見ると、「周辺の騒音の状況」が最も高く、次いで「近隣の住人層」「カーテンや照明のサイズ選びをするための、窓幅や天井高」などが上位に挙がりました。こちらに対する属性は「オンラインでの内見・対面での内見併用者」が最も多いという結果となりました。最も手間をかける属性のため、「最初から把握できていれば無駄な内見をせずに済んだのに…」ということなのでしょう。
まとめ
首都圏を中心とした物件価格の高騰により、賃貸住宅の家賃および管理費が上昇している今、入居希望者の住まい選びも、より慎重になっていると考えられます。
今後の賃貸経営の戦略においては、それぞれの属性にあった条件や設備はもとより、周辺の環境や状況といった情報、オンライン・リアル両面でのアプローチなども整理・整備しておく必要があります。今回のこうしたアンケート結果を上手く経営に活用していきましょう。
※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年10月27日時点のものです。
取材・文/御坂 真琴
ライタープロフィール
御坂 真琴(みさか・まこと)
情報誌制作会社に25年勤務。新築、土地活用、リフォームなど、住宅分野に関わるプリプレス工程の制作進行から誌面制作のディレクター・ライターを経てフリーランスに。ハウスメーカーから地場の工務店、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、販売促進ツールなどの制作を手がける。