DX、物価高、災害リスク…変わる住まい選びの価値観。住まいへの意識調査でわかった“選び方”のリアル

円安や物価高などの経済環境の変化、温暖化等の環境問題への対応、そしてデジタル技術の進化。近年、日本の不動産市場はこの三つのトレンドに強く影響を受けていると言えます。今回、全国宅地建物取引業協会連合会が全国の20~65歳の男女5,000人を対象に実施した「住まいに関する定点/意識調査」から、今後の不動産市場の動向を賃貸住宅に焦点をあてて探っていきます。
「持ち家派VS賃貸派」双方の主張から見えてくること

「あなたは『持ち家派』『賃貸派』どちらですか。現在のお住まいの関係なく教えてください。」という質問をしたところ、「持ち家派」と答えた方は63.0%。2021年(79.6%)から5年連続の減少トレンドとなりました。
理由として挙げられたのは「家賃を払い続けることの無駄感」が51.0%でトップ。「落ち着きたいから」(40.5%)、「老後の住まいが心配だから」(32.3%)が続く結果となりました。
他には「持ち家を資産と考えているから」(27.3%)、「賃貸は賃料の値上げや退去リスクがあるから」(12.6%)など上位にランキング。生活コストの「賃料」に対してマイナスの考え方をする層が「持ち家派」を支えていると考えられます。
一方、「賃貸派」と答えたのは20.2%。こちらは2021年(20.4%)から大差なく推移しています。賃貸派とする主な理由は「住宅ローンに縛られたくないから」が36.2%で最多。次いで「税金や維持管理にコストがかかるから」(34.9%)、「不動産を所有しない身軽さがいいから」(27.5%)と、コストや地縁に縛られることを嫌う層が賃貸派を占めています。
このあたりが賃貸派の潜在層へ魅力を訴求するヒントになりそうです。他には「天災が起こった時に家を所有していることがリスクになると思うから」(25.3%)、「仕事等(転勤、転職、退職など)の都合で引っ越しする可能性があるから」(17.5%)、「家族構成の変化で引っ越しする可能性があるから」(10.2%)など、未来に対して柔軟に対応したいと考える層が賃貸派となっていると考えられます。
災害リスクと住まい選び。防災意識はどこまで浸透した?

「天災に対する住まいの意識について」という質問に対しては、「緊急避難場所や防災マップ・ハザードマップを意識するようになった」(33.5%)、「築年数や構造(免震・耐震)について考えるようになった」(33.3%)、「地盤などの状況を意識するようになった」(29.3%)など前年から微減してはいるものの、居住エリアを選ぶ際には防災面を必ず確認するなど、前年に引き続き防災意識は高く推移しています。
また、ハザードマップの認知度は全体で54.1%と半数を超える結果となっていますが、これを年代別に見てみると20代が40.7%、30代が45.5%と若年層で低く、50代で66.3%、60代以上では73.8%と大幅に上昇していることがわかります。
さらにハザードマップについて「知っているが、見たことがない」(20代・33.3%)、30代では認知度自体が前年から減少。子育て世代の防災意識には特に課題が見えます。
物件情報、電子契約、省エネ。住まい選びの変化は?
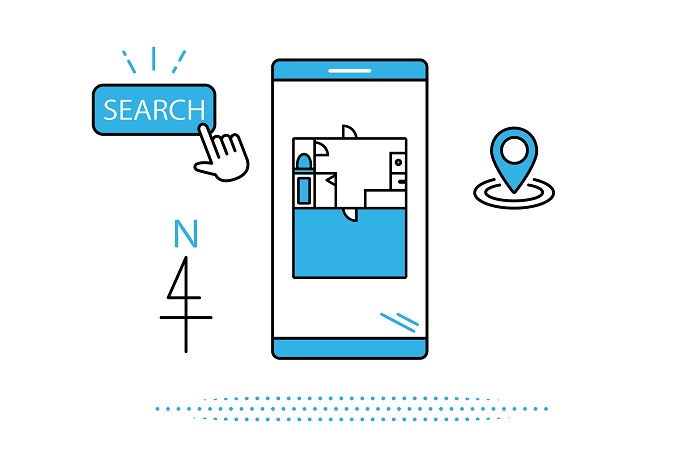
写真・動画・相場情報…物件選びで“ほしい情報”
「物件情報の入手の際、基本情報以外に『あると便利な』情報はなんですか。(複数回答)」との問いに対しては、依然として「物件の写真」が54.3%と半数を超えて最多に。さらに「物件紹介の動画」が前年から4.9ポイント増の26.3%に上昇しています。
また、「周辺物件の相場」は前年から2.7ポイント増の36.9%。こちらはここ数年の間で初めての上昇となりました。不動産価格の高騰に伴い、当該物件周辺の相場も比較・確認するようになったことで、その物件価格が妥当かどうか判断する傾向が強まっていることが示唆されています。
電子契約は普及する?若年層に広がる不動産取引

「2022年5月に不動産取引において電子契約が解禁されました。あなたは、不動産取引の際に電子契約を利用したことがありますか。」との質問をしたところ、「利用したことがある」と回答した方は、わずか15.0%という結果に。
ただ年齢別に見ると、20代(32.6%)、30代(21.0%)と、徐々にではありますが若年層で浸透しつつあることが伺え、今後は主流となることも想像できます(参考:40代・8.6%、50代・5.0%、60代以上・3.1%)。
省エネ性能表示制度が始まって1年…認知度はまだ半数以下
「2024年4月から建築物の省エネ性能表示制度が開始されました。これは、建築物の省エネ性能を客観的な数値(星印等)で評価できる制度です。あなたはこの制度を知っていますか。」と、省エネ性能表示制度の認知度を調査したところ、「全く知らなかった」が最多の46.1%となり、開始から1年以上経過した本制度ですが、半数近くの人に届いていないことが浮き彫りになりました。
その一方で、「今後、住まい選びの参考にしたい」との声も合計で21.5%あり、本制度への潜在的な関心も一定数あることが確認できます。今後、一層の周知徹底が期待されます。
家賃補助・バリアフリー…住まい支援に求められること
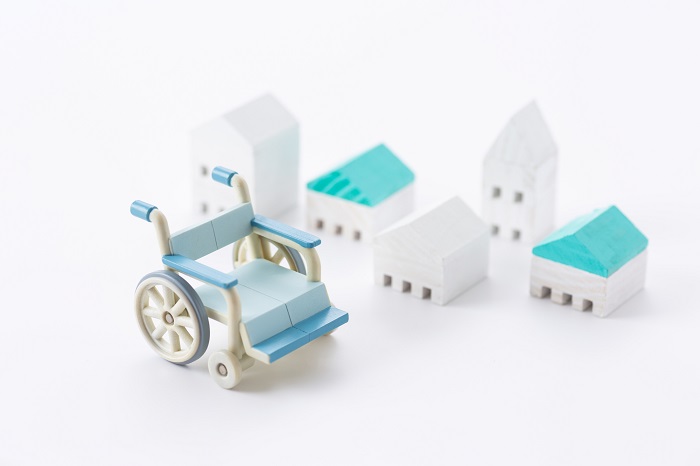
「高齢者や障がい者、子育て世帯など様々な人が安心して暮らせる住宅について、どんな支援や制度があると良いと思いますか(複数回答)」との質問では、「家賃補助や住宅購入支援金の拡充」(33.4%)、「バリアフリー住宅への改修費用補助」(33.3%)が高ポイントで上位に。金銭的な支援が期待されているのは、最近の物価高による影響が大きいことが伺えます。
さらに「見守りサービスや緊急時対応システムの整備」(24.1%)、「入居時の保証人制度の柔軟化」(23.0%)、「医療・介護サービスと連携した住宅の整備」(21.6%)、「入居審査の柔軟化」(18.6%)など、少子高齢化が進む現状に、なんとか対応してほしいという行政への強い要望も見えてきます。
まとめ
不動産を購入するにしても、賃貸住宅を借りるにしても、2025年は「価格の高騰」が重要なキーワードになりました。加えて「消費者ニーズが多様化している」ことも特徴で、この2つが喫緊の課題を言えそうです。
これらには行政はもちろん、不動産に携わる業界全体で取り組まねばならず、価格高騰に対する支援金の拡充、災害に強い住まいの開発・提案、デジタル化をはじめとした利便性の向上なども重要なポイントと言えます。
膨大な情報が目まぐるしいスピードで広がっていく現代。加えて、今までにない速度で日本人の人口が減り続けている中で、賃貸住宅オーナーも情報感度をより鋭敏にし、消費者の多様化したニーズに応えるサービスをより拡充させていく必要があります。先んじて行政や業界に働きかける「攻めの戦略」を打つことが必要になるでしょう。
※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年10月15日時点のものです。
取材・文/御坂 真琴
ライタープロフィール
御坂 真琴(みさか・まこと)
情報誌制作会社に25年勤務。新築、土地活用、リフォームなど、住宅分野に関わるプリプレス工程の制作進行から誌面制作のディレクター・ライターを経てフリーランスに。ハウスメーカーから地場の工務店、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、販売促進ツールなどの制作を手がける。




















