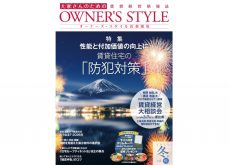収益を維持するために知っておきたい!建物の修繕周期と設備の交換周期、各費用の目安

「築20年も超えたし、建物があと何年もつかな」と悩むオーナーは多いのではないでしょうか?実は、きちんと対応していけば、長く収益を生み続けられるのが今の賃貸住宅。ずっと入居者に選ばれ続けるために、知っておきたい修繕の周期や費用の目安を紹介します。

東京都新宿区出身、早稲田大学商学部卒業。石膏ボードメーカーに10 年勤務、二級建築士資格を取得後、現職へ。築古物件の課題分析・満室化・改修提案の実績多数。
修繕で不可欠なのは防水対策!長期活用時代の新ポイント
建物修繕で最も重要な箇所が、外壁や屋根の補修・塗装。規模が大きく重要性が高いからです。
「建物にとって一番の敵は水。鉄筋コンクリートにしても鉄骨にしても水にさらされるとさびてしまう。木造でも鉄でできている部分は多く、木は水で腐食する。構造部分の性能や寿命に大きな影響を与えます。そのため防水・防湿の対策が根幹が根幹になります」
また、今まで見落とされていたのは、給排水やエレベーターなどの電気設備関係。
「どちらも修繕周期が30~40年と長く、これまでは修繕する前に解体や建て替えになっていました。実例が世の中にあまり出回っていないため、一般的な金額の目安は出しにくいからです」
長期活用するには、この分野の準備も欠かせません。個々の条件に応じて検討しましょう。
主な設備の交換周期、費用の目安

建物の修繕周期、各費用の目安

※修繕・交換周期と工事単価は、使用する部材・材料・設備等のグレードにより異なるため、幅を持たせて表記しています。 出典:国土交通省 住宅局「賃貸住宅の計画的な維持管理及び性能向上の推進について~計画修繕を含む投資判断の重要性~」、(株)市萬「管理会社の一級建築士が教えるずっと安心‼!選ばれ続ける建物修繕」
建築専門家への相談、建物診断も忘れずに
ここで示した修繕周期や費用は、あくまでも標準的な設備仕様の場合の目安。建物の立地・環境、利用状況で前後してきます。劣化がそれほど進んでいないのに、修繕周期に合わせて実施すれば、過剰修繕になるおそれもあります。
建物の劣化状態を診断し、必要な内容とタイミングの精査が大切です。建物診断をしたら長期修繕計画を立てる必要があります。当初のプランがずっと通用するわけではないので、5年、10年に一度は見直しましょう。
また、既存物件すべてを長期活用できるわけではありません。1981年5月31日以前に建築確認を受けた“旧耐震設計”の建物は注意が必要です。耐震改修のコストや耐久性との関係で長期活用が採算に合わない可能性があります。
一方で、賃貸ニーズが強くて高い賃料を得られる好立地の場合、賃貸収支より相続対策を重視している場合など、建て替えにメリットがあるケースも。個別に耐震診断を受けて活用方法を検討した方が良く、建物の専門家への相談は欠かせません。
「建物を長く持たせようという気持ちになったら、築年を問わずに専門家に相談してください。迷っている人でも、築20年を超えて一度も大規模修繕をしていない場合は、早めの相談がおすすめです」
※この記事内のデータ、数値などは2021年2月16日時点の情報です。
文/木村 元紀 イラスト/アサミ ナオ