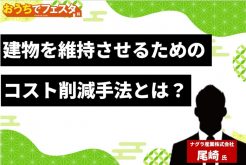家賃滞納が発生!強制退去させることはできる?条件やかかる費用などを解説

賃貸経営におけるリスクのひとつとして備えておきたいのが、入居者の家賃滞納。家賃滞納が発生したとき、賃貸オーナーとしてはどのように対処するべきなのか、ご存知ですか?家賃滞納に対して強制退去の措置をとれるのはどのようなケースなのか、家賃支払いの交渉から強制退去への手続き、かかる費用などについて解説します。
家賃滞納が発生!強制退去させることはできる?

家賃滞納での強制退去は可能
結論からお伝えすると、家賃滞納による強制退去は可能です。しかし強制退去を実行するには正当な理由が必要で、実行するためにはいくつか条件があります。それらをすべてクリアしたうえで、きちんと法的な手続きをしてから、最後の手段として実行することになります。
強制退去とは、賃貸人(賃貸オーナー)が賃借人(入居者)に「建物明渡請求」を求め、裁判所からの判決をもとに強制力をもって賃借人を退去させることを指します。強制退去は、家賃滞納をはじめとした入居者によるトラブルを解決する最終手段となります。
強制退去を実行できる条件

強制退去を実行する前に、賃貸人(賃貸オーナー)は話し合いや内容証明郵便など、できる限りの交渉を試みます。これらの交渉については後の項で詳しく触れますが、任意での明け渡し請求に応じない場合に、裁判所へ「建物明渡請求」の訴訟を起こすことになります。
裁判所に主張が認められた場合、賃借人(入居者)に退去が求められます。この時点でも退去しない場合、判決に基づき、執行補助者が荷物などを運び出して強制的に退去させる「強制執行」が行われます。
裁判所が「建物明渡請求」の訴えが妥当であると判断する条件には、以下のようなケースがあります。
家賃滞納について、法律で具体的な期間は定められていません。しかし過去の判例から、3カ月以上の家賃滞納がある場合に、強制退去が認められやすくなります。
しかしながら家賃滞納が3カ月を過ぎれば即契約解除ができるというわけではありません。滞納1カ月~2カ月の間に連絡や内容証明郵便による請求を行い、それらが無視され続ければ「支払う意思のない悪質な家賃滞納」とみなし、「建物明渡請求」の訴えが通りやすくなります。
賃貸借契約は、貸主と借主の双方の信頼関係によって成り立っている法律上の取り決めです。この信頼関係が崩れてしまった、つまり破綻しているとみなされた場合、強制退去が認められます。
強制退去が認められないケース

前項の通り、強制退去が認められる家賃滞納の期間は3カ月が目安です。「忙しくてうっかり振込みを忘れた」「たまたま口座の残高が不足していた」など一時的かつ短期間の滞納は、強制退去の段階ではありません。
入居者の失業など特殊な事情ですぐには家賃が払えないものの、分割払いなどで支払うことに貸主が合意している場合などは前述の「信頼関係の破綻」にあたりません。どのように家賃を支払っていくかは双方の話し合い次第ですが、あくまで支払いの意思があるとみなされるうちは、一方的な明け渡し請求は難しいでしょう。
家賃の支払いや滞納について、契約書に明記がなかったり、定められた管理や備品の修理などをオーナー側がきちんと行わず、入居者の生活に支障が出ていたりした場合などは強制退去が認められないケースもあります。
また、いくら家賃滞納があったとしても、オーナーの督促方法に法的な問題がある場合は強制退去の執行が難しくなります。具体的には、勝手に部屋に入って家財を持ち出す、通告なしに鍵を交換するなどの脅迫行為などです。
強制退去以外の対応策

強制退去は最終手段として、家賃滞納者へのそれ以外の対応策には以下のようなものがあります。
簡易裁判所に申し立てて「支払督促」の手続きを行います。その申し立てに基づいて簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度で、裁判所に出向くことなく書類審査のみでできます。もし支払督促受領後2週間以内に相手方が異議申立てをした場合、民事訴訟手続きに移行することになります。
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易裁判所の訴訟手続きです。原則1回の期日で審理を終え、即日判決が出ます。訴訟の中で妥協点を見出し、和解というケースもあります。
家賃滞納トラブル発生時の相談先は?
家賃滞納を放置してしまうと、時間が経つにつれてどんどん回収が難しくなったり、自身の経営状態が悪化したりすることになります。家賃滞納が起こったらできる限り速やかに、しかるべきところに相談しましょう。
相談先としてはまず、不動産や債権回収に詳しい弁護士が考えられます。弁護士を通して督促状を送ってもらったり、滞納者との交渉や法的手続きなどをまかせたりすることができます。
無料で相談できる窓口としては(公財)、全国賃貸住宅経営協会が運営しているコールセンターがあります。弁護士に相談する前にまず対処法を聞きたいときや、弁護士に相談するべき状況なのかを知りたいときなどに利用すると良いでしょう。
強制退去の前に。家賃滞納者への円満解決アプローチ
「家賃滞納は困るけれど、穏便に解決できるのであればそうしたい」と願うのは当然のことです。この項では、強制退去の前に家賃滞納者に対してできること・するべきことを解説します。
まずは支払い交渉を。基本的な流れ

家賃の支払い予定日から数日が過ぎただけでは、入居者が単に忘れているだけであったり、入院・旅行などでたまたま支払いができなかったりした可能性を否定できません。まずは家賃が支払われていないことを入居者に知らせ、事情を把握する必要があります。
家賃を自動引き落としにしている場合は、引き落とし日から1〜3日程度で銀行から滞納リストが上がってきます。そこから入居者へ電話やメールで連絡を行います。
同時に家賃支払い通知を送付もしくはポスティングして文書でも知らせます。うっかり忘れていた人やたまたま口座残高が不足していた人からは、この時点で支払いがあるはずです。
家賃滞納は、大部分が「うっかり忘れた」「バタバタして残高を確認していなかった」などの理由で発生しているので、支払い予定日が過ぎたら早めに電話連絡をすることをおすすめします。
これまできちんと家賃を支払っていた人であれば、万が一、部屋で倒れているなどの可能性もあります。早期発見のためにも「そのうち払ってくれるだろう」と連絡は先延ばしにしない方が良いでしょう。

家賃滞納から1週間以上、連絡がとれない状態が続くのであれば、督促状を送ることになります。督促状に明記するのは物件名や部屋番号の他、滞納金額、振込先など。最初の督促状には、入れ違いで入金された場合のお詫び文なども入れ、丁重な文面にします。
1回目の督促状を送っても連絡や支払いがない場合は、2回目の督促状を送ります。タイミングの目安としては滞納から1カ月以内で、「〇月〇日までに入金が確認できない場合、連帯保証人様に連絡させていただきます」などの文言を入れ、督促の意思を強めた文面にするのが一般的です。
督促状では支払い期日を定めて連絡しますが、事情によっては入居者に支払いの意思があっても一括での支払いが難しい場合があります。本人ときちんと連絡がとれていて支払いの意思があること、支払いの目途が付きそうなことが確認できれば分割払いなど、ある程度の譲歩も検討しましょう。
2回目の督促状を送っても連絡が取れなかったり、分割払いの期日を守らなかったりしたなどの場合には連帯保証人に連絡を取ります。連帯保証人に迷惑をかけたくない、知られたくないなどの事情のある入居者からは、この時点で入金があることも。
連帯保証人の代わりに保証会社を利用している場合は、契約で定めた期間内に保証会社へ代位弁済を請求します。保証会社から家賃の立て替え払いがあり、入居者へは保証会社から督促が行われます。
支払い交渉時のポイントと注意点
支払いの交渉はあくまで冷静に、複数の連絡手段をもって行い、連絡の記録を残しておくようにしましょう。家賃滞納は賃貸オーナーにとって迷惑であることは確かですが、一方的な交渉にせず対話を心がけることで、今後の家賃支払いや退去に応じてくれる可能性も高くなります。
タブーなのが、入居者の職場に連絡をして勤務先に滞納があることを伝えたり、深夜・早朝の電話や訪問など脅迫めいた督促です。他の入居者の目につく玄関ドアへの貼り紙なども、トラブルに発展しやすいのでやめましょう。入居者の生活を脅かすような行為は、後に裁判に発展したときオーナー側に不利にはたらきます。
家賃滞納者との交渉決裂…。強制退去を執行する流れ

連絡や督促が無視され続けるなどして、話し合いにならないこともあるかもしれません。交渉が決裂した場合、次のような流れで強制退去まで進むことになります。
内容証明郵便で賃料督促、賃貸借契約解除を送る
最初の支払い予定日から2カ月目が経過、つまり2回目の家賃滞納が発生したあたりを目安に、内容証明郵便で賃料の督促を行います。
内容証明郵便とは、いつ・どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する郵便物。のちに訴訟になった時に、実際に督促を行ったという履歴を残すことができます。
内容証明郵便では、期日までの滞納賃料の督促と、それまでに支払いがない場合は賃貸契約を解除する旨を明記します。文書の標題も「督促状」から「催告状」に変わり、弁護士に依頼して弁護士名で送ってもらうこともできます。
契約解除と明け渡し請求訴訟の手続き
催告書で指定した期間までに滞納者が支払いをしない場合、賃貸借契約は解除されたことになります。その後は退去するように促しますが、契約が解除されたからといって無断で鍵を変えたり、部屋の私物を撤去したりすることはできません。
契約が解除されても滞納者が部屋に居座る場合、賃貸オーナー側は部屋の明け渡し請求訴訟を起こすことで、法的に退去を求めることができます。
状況によっては、明け渡しの裁判の前に「占有移転禁止の仮処分」を行います。これは、裁判所に申し立てて、滞納者以外が部屋を占有することを禁止する手続きです。

訴訟は当事者にしか効力が及ばないため、明け渡し判決が出たとしても部屋を又貸しされた場合などに強制執行ができなくなってしまいます。悪質な滞納者の場合、強制執行妨害行為として第三者が部屋に居座ることが実際にあり得るため、それを防ぐための措置です。
明け渡し請求訴訟では、訴状に契約書などの証拠書類、不動産登記簿謄本などを添付して提出すると、1~2週間ほどで裁判所から裁判の期日を指定されます。期日決定後に滞納者に呼び出し状が送られ、裁判となります。弁護士に依頼している場合は、当日は賃貸オーナー自らが裁判に行く必要はありません。
明け渡し判決後の強制執行申立
滞納者が裁判に出頭すれば、強制執行を伴わない任意の立ち退きの合意が得られる場合もあります。実際は答弁書も出さず、出頭しないケースも多く、その場合には裁判所が原告(賃貸オーナー)の請求を認める判決が出ます。
明け渡し判決が出た後も自主的に退去しない場合は、最終手段である「強制執行の申し立て」を行うことになります。これは、明け渡し請求で出た判決に執行文を付与する手続きです。
裁判所からの立ち退き勧告
強制執行の申し立てが裁判所に受理されると、裁判所から滞納者へ立ち退きの催告書が送られます。これが滞納者に届いていることを証明するために、送達証明書も申請します。
強制執行
立ち退き勧告を受けても退去しなかった場合、裁判所の執行官が専門業者とともに部屋を訪れ、家具や家財を搬出します。この後、鍵を交換して強制執行は完了です。家財の運搬や一時保管など、強制執行にかかる費用は、賃貸オーナーがいったん立て替えて負担することになります。
2020年4月の民事執行法改正により、住居の明け渡しを伴う強制執行において、「生活の本拠性」の確認や社会福祉との連携が義務化され、生活困窮者への配慮が強化されました。
執行官は、実施前に福祉事務所に連絡をとり、本人が行き場を失うことがないよう配慮する必要があります。そのため、強制執行に至るまでにはより慎重な運用が求められているのが現状です。
強制退去にかかる費用

ここまでの内容で、強制退去には時間も手間も費用もかかることがおわかりいただけたと思います。もし強制執行まで進んだ場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。段階を追って見てみましょう。
内容証明
内容証明は、督促状を内容証明郵便で送るための費用で、2025年4月時点では郵便料金に一般書留480円と内容証明480円、配達証明350円が加算されます。50gまでの定形郵便が110円なので、合わせて1,420円となります。
裁判
明け渡し請求訴訟の手続きにかかる費用の内訳は、訴状に添付する印紙代と予納郵便切手代、証拠書類を揃えるための費用です。印紙代は賃貸物件の固定資産税評価額によって、予納郵便切手代は裁判所によって変動しますが、トータルで3万円程度が目安となります。
弁護士依頼
強制退去の手続は複雑なため、弁護士に依頼する場合が多いと思われます。依頼費用は弁護士事務所によって大きく変わりますが、相談料、着手金、報酬金などすべてを合わせて30万円~60万円程度がかかります。
強制執行
明け渡し訴訟で判決が出て、実際に強制退去を執行するのにかかる費用は30~50万円程度になります。執行官への予納金が東京地裁の場合6万5,000円、撤去や運搬作業を行う執行補助者の人件費、段ボール大やトラックの手配日、保管・廃棄費用などがその内訳となります。
ここまでで、強制退去には全体で100万円近い費用がかかることがわかりました。これらのうち弁護士費用以外は民事執行法の定めにより、滞納者に請求が可能です。滞納者には必ず転居先を聞いておくようにしましょう。
ただし、家賃滞納が経済的困窮によるものであった場合、執行費用の支払いが難しいことも考えられます。さらに、滞納者に自己破産をされてしまうと滞納分の家賃の回収もできなくなってしまいます。
強制退去となる前に。家賃滞納トラブルを防ぐ方法
時間も費用もかかり、やらずにすむなら避けたい強制退去。精神的負担も重いため、家賃滞納はできるだけ未然に防ぎたいものです。
家賃滞納トラブルを防ぐためには、入居審査を厳格に行ったうえで契約時に家賃の支払いや滞納した場合の対処についてしっかり説明することがまず大前提。
そのうえで、入居者との定期的なコミュニケーションによって信頼関係を築くことができれば、滞納が起こる前に相談があるなど、早い段階で対応できる可能性が高くなります。
家賃債務保証会社の利用

入居審査の徹底や入居者との信頼関係構築は重要ではあるものの、100%うまくいくとは限りません。いざというときのリスクヘッジとして有効なのが、家賃債務保証会社の利用です。
入居者が家賃を滞納すると代わりに家賃を支払ってくれるサービスで、入居者は保証料を払って家賃債務保証会社と契約します。

家賃債務保証会社が家賃を立て替えてくれることが賃貸オーナーにとって最大のメリットとなります。滞納が発生した場合の督促業務なども家賃債務保証会社が行います。
大家さんにとっては督促業務や滞納リスクを減らせるありがたいサービス。最近は連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社との契約を入居条件にしている物件が増えています。
様々な理由によって連帯保証人が立てられない場合でも、家賃債務保証会社を利用することで家を借りられるのが入居者にとってのメリットです。信用を証明しやすいため、選べる物件の幅も広がると言えるでしょう。

家賃滞納が起きた場合、家賃債務保証会社に代位弁済を請求することで、家賃が立て替えられます。しかしこの代位弁済請求にも期限があり、滞納から一定期間が過ぎてしまうと家賃を保証してもらえません。さらに、倒産などで回収不可能になってしまうリスクもデメリットとなります。
入居者にとってのデメリットとしては、家賃債務保証会社に支払う保証料の負担があります。相場は初期費用が家賃の50~100%程度と、決して安くはありません。また、家賃債務保証会社との契約にも審査があり、過去の滞納歴でブラックリストにのっている場合や、収入によっては審査に通らないこともあります。
また、家賃債務保証会社との契約トラブルが増加していることから、国土交通省は「家賃債務保証業者登録制度」を2020年に導入しました(※任意制度)。
この制度では、適正な審査・契約書の記載事項・情報提供義務などがガイドラインとして明文化。登録業者を選ぶことで、貸主・借主双方がトラブルを避けやすくなっています。
まとめ
(公財)日本賃貸受託管理協会の「日管協短観」によると、2023年度は全国の月末での1カ月滞納率が1.2%、2カ月以上の滞納率は0.5%。前年度よりも上昇しています。保証会社の必須割合も93%と、滞納リスクを避けるために、保証会社の利用が定着してきていることがわかります。
強制執行による立ち退きは賃貸オーナーにとっても手痛い出費となり、時間も精神的ストレスもかかります。強制退去となる前に、家賃滞納のリスクを防ぐためのできる限りの手を打っておくことがとても重要です。
※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2024年4月1日時点のものです。
取材・文/石垣 光子
ライタープロフィール
石垣 光子(いしがき・みつこ)
情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。
年4回無料で賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」をお届け!