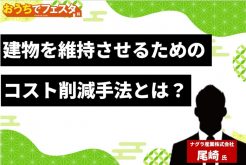家賃・設備・立地…賃貸住宅が選ばれる理由と妥協点は?国交省調査から今の賃貸市場を知る

国土交通省が毎年行っている「住宅市場動向調査」。住宅に関する消費行動や資金調達についての実態を把握し、今後の政策に生かすためのものです。7月に発表された令和6年度の調査結果から、賃貸住宅に関する部分を抜粋してご紹介します。
賃貸住宅入居者の年齢・世帯構成・年収の傾向

調査の対象となったのは首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、中京圏(岐阜県、愛知県、三重県)、近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県)の三大都市圏で、2023年4月~2024年3月に民間賃貸住宅に入居した世帯。
まず、民間賃貸入居世帯とはどのような属性なのでしょうか。世帯主の年齢は「30歳未満」が34.6%で最も多く、次いで「30代」が21.7%。平均年齢は38.9歳でした。
居住人数は「1人」が41.1%で最多で、次いで「2人」が35.6%、「3人」が 14.2%。世帯あたりの平均居住人数は1.9人です。このうち配偶者がいる世帯は41.2%、子育て世帯の割合は17.6%で、若者夫婦世帯の割合は12.3%となっています。
ここでの「子育て世帯」とは高校生以下の居住者がいる世帯を、「若者夫婦世帯」とは世帯主年齢が39歳以下の2人世帯のうち、65歳以上の居住者および高校生以下の居住者がいない世帯を指します。
65歳以上の高齢者がいる世帯は11.3%で、そのうち60.6%が高齢者のみの世帯。平均居住人数は1.1人となっていることから、ひとり暮らしの高齢者が多いことがわかります。
世帯主の職業は「会社・団体職員」が66.3%で最も多く、次いで「自営業」が8.9%。世帯年収(税込み)は「400 万円未満」が 33.9%で最も多く、次いで「400万円以上 600万円未満」が23.6%。平均世帯年収は486万円でした。
選択理由は「家賃が適切だったから」が最多の55.5%
住み替えに関する意思決定において、「住宅の選択理由」の上位は以下のような結果となりました。
| 住宅の選択理由(複数回答) | ||
| 1位 | 家賃が適切だったから | 55.5% |
| 2位 | 住宅の立地環境が良かったから | 31.0% |
| 3位 | 交通の利便性が良かったから | 29.8% |
| 4位 | 住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから | 27.2% |
| 5位 | 職場から近かったから | 22.1% |
トップ5は3年前(令和4年度)から変わっていませんが、1位の「家賃が適切だったから」は46.7%→51.1%→55.5%と少しずつ増えています。
一方で、2位と3位の立地とアクセスに関する項目は直近3年で減少傾向。4年前(令和3年度)は「住宅の立地環境が良かったから」が52.7%で1位だったのが逆転し、ここ3年で立地よりも家賃が重視されるようになったことがわかりました。
設備等に関する選択理由は「間取り・部屋数が適当だから」が 67.9%で1位。次いで「住宅の広さが十分だから」「台所の設備・広さが十分だから」「住宅のデザインが気に入ったから」「浴室の設備・広さが十分だから」が続き、トップ5の顔ぶれは令和2年度から変わっていません。
部屋探しで妥協したのは「家賃」「住宅の広さ」「部屋数」

住宅の選択にあたって妥協したものは「家賃(予定より高くなった)」が最も多く27.2%。「住宅の広さ」19.5%、「間取り、部屋数」17.5%が続きます。
住み替えについて、住み替え以前に住んでいたのは「民間賃貸住宅」が 52.1%で最も多く、次いで「親・兄弟姉妹など親族の住宅」からの住み替えが 27.7%でした。
住み替え前も賃貸住宅に住んでいた世帯の、住み替え前の家賃は平均で月額7万3,510 円。月額家賃の中央値は 6万5,000 円でした。住み替え前の賃貸住宅での平均居住期間は8年です。
住み替え前後で住んでいる住宅の延床面積を比べてみると、住み替え前が平均 63.8㎡、後が平均49.7㎡と、14.1㎡狭くなったことがわかりました。しかし、住み替えによって最寄りの公共交通機関までの距離は0.6Km、通勤時間も7.4分短縮できています。
平均築年数は19.9年。宅配ボックスの設置率は30.5%
築年数については、「平成27年以降」が26.2%、次いで「昭和60年~平成6年」が18.7%。平均築年数は19.9年でした。

コロナ後に定着した在宅勤務のためのスペースについては「仕切られてはいないが在宅勤務に専念できるスペースがある」世帯が22.1%、次いで「在宅勤務に専念できる個室がある」世帯が19.9%。「在宅勤務に専念できる仕切られたスペースがある」6.0%と合わせると、48%は在宅勤務ができるスペースを備えていることになります。しかし前年度(令和5年度)の61.2%からは減少しました。
宅配ボックスの設置については、「設置している」世帯が30.5%。こちらも前年度の36.8%よりも減っています。
平均家賃は7万7,677円。家賃負担を感じる人が過半数
住宅の選択にあたり、家賃が予定より高くなったと回答した人が多くいましたが、ここで費用について見てみましょう。
まず、入居した賃貸住宅の家賃の平均は月額7万7,677 円で、中央値は7万円。やはり住み替え前の平均家賃より月額4,167円高く、中央値は5,000円高くなっています。このうち勤務先からの住宅手当を受けている世帯は23.8%で、住宅手当を受けている世帯の住宅手当額の平均は月額3万1,428 円でした。
敷金/保証金があった世帯は57.7%で月数は「1ヶ月ちょうど」が61.7%で最多となりました。礼金があった世帯は42.6%。礼金の月数は「1ヶ月ちょうど」が65.0%で最多でした。礼金については地域差も大きく、首都圏が49.0%であるのに対し、中京圏では20.0%、近畿圏で41.9%となります。

更新手数料についても同様の傾向で、全体では44.7%が更新料「あり」ですがその割合は首都圏60.5%、中京圏16.7%、近畿圏26.5%と地域差があります。
家賃について「非常に負担感がある」6.8%と「少し負担感がある」46.1を合わせて52.9%が家賃に負担を感じていました。前年度である令和5年度より2.6%増えています。
賃貸で困ったことは?契約・入居・退去のトラブル実態
最後に、賃貸住宅(普通借家)に関して困った経験についての質問。複数回答で以下が上位(10%以上)の結果です。
| 賃貸住宅の契約時に関して困った経験(複数回答) | ||
| 1位 | 敷金・礼金などの金銭負担 | 56.1% |
| 2位 | 連帯保証人の確保 | 23.6% |
| 3位 | 印鑑証明などの必要書類の手配 | 14.6% |
| 賃貸住宅の入居時に関して困った経験(複数回答) | ||
| 1位 | 近隣住民の迷惑行為 | 39.0% |
| 2位 | 家主・管理会社の対応 | 24.4% |
| 賃貸住宅の退去時に関して困った経験(複数回答) | ||
| 1位 | 修繕費用の不明朗な請求 | 22.0% |
| 2位 | 家賃、敷金の清算 | 13.8% |
| 3位 | 中途解約時の追加金銭の請求 | 10.6% |
入退去時は請求などお金にまつわること、入居中は近隣トラブルやそれらに対する家主側の対応に困っていることがわかりました。
まとめ
昨今の家賃上昇を反映してか、住宅の選択理由などに家賃に関する項目の割合が増加した令和6年度調査。実際に住み替え前後の平均家賃も4,000円程度増えており、首都圏ではさらにこの傾向が強まっています。
国交省のホームページでは、直近5年間(令和2年度~6年度)までの経年変化や都市圏ごとの細かい数字も確認できます。物件をお持ちの地域や、気になる項目の変化をチェックしてみてはいかがでしょうか。
※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年8月20日時点のものです。
取材・文/石垣 光子
ライタープロフィール
石垣 光子(いしがき・みつこ)
情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。